皆さん、こんにちは。神奈川県 横浜市 南・港南支部所属 行政書士 近田知成です。
第54回目記事投稿となる今回は、【自筆証書遺言における検認手続きとは?】をテーマにお送りしていきたいと思います。
 自身の生前の意思として、自筆による遺言書作成をお考えの方もおられるかと思います。自筆証書遺言は公正証書遺言に比べ費用的にも時間的にも簡便な型で遺すことが出来ますので、『遺言書作成を思い立ったがあれこれ段階を踏んでの過程が面倒だ』とお感じの方にはおすすめの方法となるでしょう。
自身の生前の意思として、自筆による遺言書作成をお考えの方もおられるかと思います。自筆証書遺言は公正証書遺言に比べ費用的にも時間的にも簡便な型で遺すことが出来ますので、『遺言書作成を思い立ったがあれこれ段階を踏んでの過程が面倒だ』とお感じの方にはおすすめの方法となるでしょう。
民放所定の形式に則り(2018年現在においては)【自筆にて全文を作成】し、【記名押印】は必要となりますが、公証役場での手続き等はありませんし、公正証書遺言では必要となる各種手数料も自筆証書ならば考慮の埒外におく事が可能です。
(*【自筆による全文の作成】については、相続法改正により自書によらない【財産目録部分(署名・押印は必要)】の添付が可能になる等の方式の緩和が2019年1月13日より行われるようになりますので覚えておくと良いかと思います。)
関連URL:【自筆証書遺言:制度改正について】
しかしながら、この自筆証書遺言においても(公正証書遺言とはまた別の点で)注意すべきポイントがあります。
それは【検認】という家庭裁判所の手続きを【遺言書開封前】に経なければならないという点です。
この点においては、(自筆証書遺言の)作成者側というよりはむしろ遺言書の保管者または発見者等(通常は相続人)の手続き上の問題となりますので、遺言書を発見された相続人側等が発見後スムーズに【検認手続き】に移行出来るよう、遺言者は遺言書を封入した封筒裏面に(又は別紙添付により)『発見後は開封せず家庭裁判所の検認を受けること』の一文を添え保管する等の工夫が必要となるでしょう。
 遺言書の保管者等は、被相続人の死亡後【相続開始地(被相続人の住所地)を管轄する家庭裁判所】に検認の申立てを行うこととなります。
遺言書の保管者等は、被相続人の死亡後【相続開始地(被相続人の住所地)を管轄する家庭裁判所】に検認の申立てを行うこととなります。
関連URL:【家庭裁判所 遺言書の検認】http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html
実際の手続きとしては、家庭裁判所が審判の期日を決定し、相続人や利害関係人を当該家庭裁判所に呼び、提出された遺言書の形式的な実情を検査し、後に検認した旨の証明書発行とともに遺言書を返還する流れとなります。
 間違えやすいポイントとして、この【検認手続き】は、提出された遺言書の【形式的要件】を満たしているか否かを検査するものであって、その遺言書の【遺言内容が有効か無効か】を検査するものではないという点が上げられます。(管轄の家庭裁判所はあくまで当該遺言書の形式や態様等【遺言書の現状を明確にする】為、この検認という手続きを行うという事。)
間違えやすいポイントとして、この【検認手続き】は、提出された遺言書の【形式的要件】を満たしているか否かを検査するものであって、その遺言書の【遺言内容が有効か無効か】を検査するものではないという点が上げられます。(管轄の家庭裁判所はあくまで当該遺言書の形式や態様等【遺言書の現状を明確にする】為、この検認という手続きを行うという事。)
また、この検認手続きの為の【遺言書提出を怠ったり】、【検認を経ないで遺言を執行した場合】等には5万円以下の過料に処せられる事も注意すべきポイントと言えます。
来年以降の相続法改正に伴い、自筆証書遺言に関連する事項についても幾つかの変更点が存在します。(この相続法改正情報については別途他の記事投稿の中でご紹介していきたいと思っています。)
しかし、当該変更点に対する留意とは別に【検認】に関しては従来通りの制度運用が見込まれますので、自筆証書遺言作成者に加え発見者となるであろう相続人等も当該手続きの必要性については十分に注意すべきであると言えるでしょう。
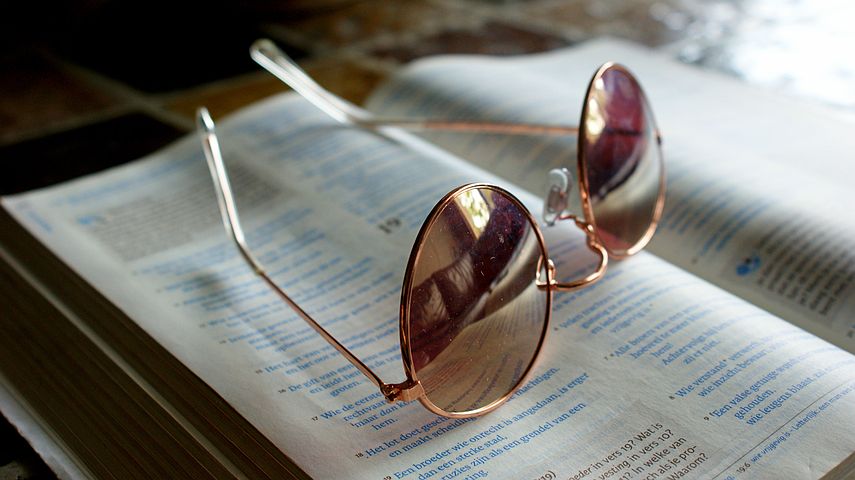











コメントを残す